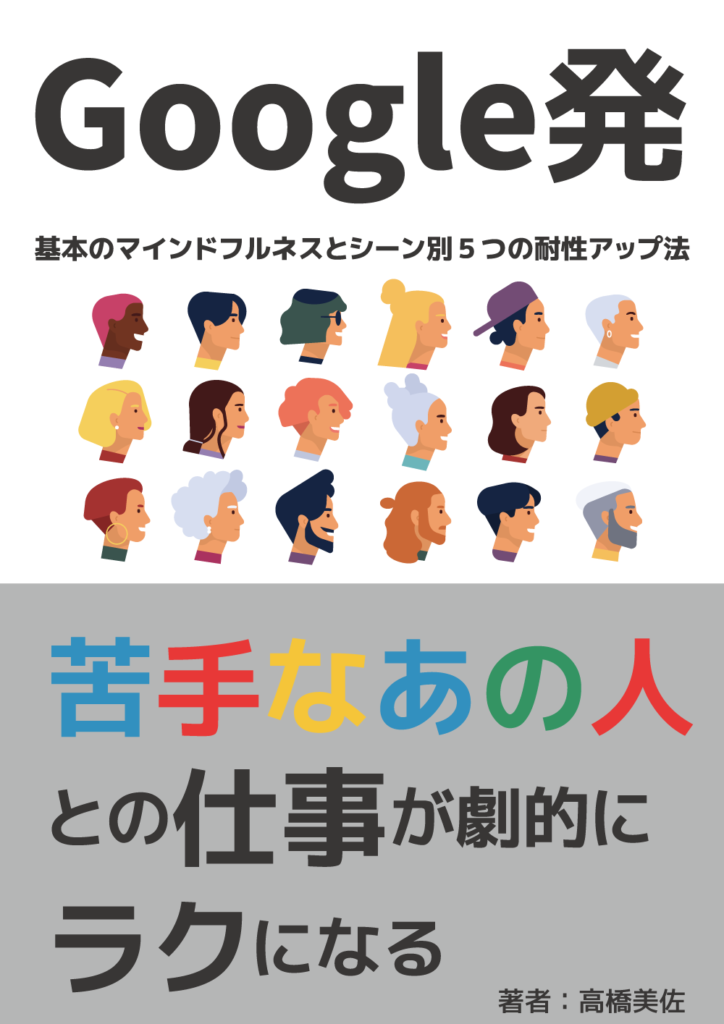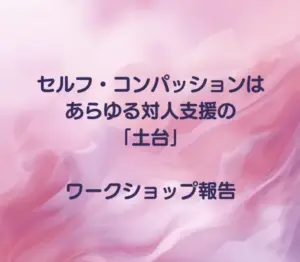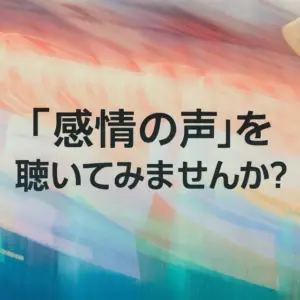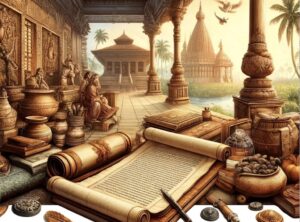最初のマインドフルネスは、ウォーキングだった

きっかけは、カバットジン博士の著書「マインドフルネス・ストレス低減法」という本を読んだことでした。カバットジン博士は、マインドフルネスを科学にした人です。
その本に歩行瞑想法という章があったんです。
それで本を読んで「こうかなぁ」「ああかなぁ」と思いながらウォーキングを始めたんですね。
なので初めからマインドフルネスを意識したウォーキングをしていました。
最初は、運動としてのウォーキングとあまり変わらない感じでした。私はもともと運動嫌いで、あまりぴんとこなかったのです。
ところが、ある一定期間続けていると突然、自分の心の状態に自覚的になる瞬間があったんです。
そこからですね、ウォーキングが楽しくなったのは。
約半年後に、著者のカバットジン博士にお会いすることがありました。その時に「先生の本は、私にとってとても良かった、ありがとうございます。」とお伝えしたら、博士は「きっと翻訳が良かったんでしょう」ととても謙虚な方でした。
それからは、毎朝の習慣として、すわってやるマインドフルネスに加えて、時間が許す限り歩くタイプのマインドフルネスも続けています。
朝にやるのは、早朝は気持ちが良いからです。歩く時間を確保するのは大変です。ですがそれだけの価値はあります。
でも、マインドフルネスは、呼吸とか歩く以外にも様々なやり方があると思っています。
さらに言えば、本当に大事にしたいポイントはマインドフルネスを実践するかどうかではなく、本当の自分にどうやって気づくかだと思っています。
本当の自分に気づく手段の1つがマインドフルネスであって、気づきさえすればそれがマインドフルネスであろうがなかろうが、どっちでもいいことなんです。
さて、ここでは、「レレレのおじさん」からの学び(!)を紹介しながら、マインドフルネスを続けると、なぜストレスが減り、楽になるのか、について書いていきます。
「レレレのおじさん」はマインドフルな人?!

最近、新たに気がついたことがあります。
きっかけは「レレレのおじさん」でした。
その前にちょっと今の季節について話します。今は秋なので道路に毎日、枯れ葉が落ちます。掃いても掃いても新しい枯れ葉が落ちてくるのでキリがありません。正直、めんどくさいなぁと思っていました。そんなとき、面白い話を聞きつけたのです。
有名なギャグマンガ「天才バカボン」の中に出てくる「レレレのおじさん」をご存知ですか?
いつもほうきを持って掃除をしていて「レレレのレー」と言っているキャラクターです。
この「レレレのおじさん」には実はモデルがあって、そのモデルとはなんとブッダの弟子で「掃除」で悟りを開いた人じゃないか、というのです!
この掃除で悟りを開いた人の話は実際の仏典にのっています。
それはこういう話です。
チューラパンタカは、ブッダのもとで修行をしていましたが、記憶力が低くて、どうしても大事な言葉を覚えられません。
自分に修行は無理だと思って、チューラパンタカはしょんぼりブッダのもとを去ろうとしました。
そのとき、ブッダが彼を引き止めて「私のところに残って掃除をしなさい」といって1本のホウキを与えるのです。
チューラパンタカは、大喜びで掃除をしているうちに「修行とは心の中に積もった『ちり』を掃き清めることだ」と気づき、それが悟りにつながった、と言うお話です。
いかがでしょうか?
実はこのチューラパンタカのお話を私は前から知っていたのですが、レレレのおじさんのモデルかも、という話を聞いて、ひらめくものがありました!
先ほども言ったように今、季節は秋、毎日のように枯葉が道路に落ちて掃除をしなければいけません。放っておくと、ご近所の人に迷惑をかけたり、雨の時には滑ったりして危ないのです。
でも、掃いたところで次から次から新しい枯れ葉が落ちてくるし、キリがない感じにちょっとうんざりしていました。
そこにレレレのおじさんが機嫌よく掃除するイメージが重なりました。
さらに、チューラパンタカの「今、自分がはき清めている『チリ』とは何をあらわすのだろう」という問いが重なりました。
それで「人の心の中の落ち葉とは、何をあらわすのだろう」と考え始めたのです。
「レレレのおじさん」が掃いているものは何?

そこで、こう考え始めたのです。次から次に落ちてくる枯れ葉は、何をあらわすのだろう。
それはきっと、心の中の小さな引っかかり、小さなストレス、つまり、何か人をイライラざわざわさせるものの象徴なのではないかと思ったのです。
イライラざわざわさせるものとは例えばこういうものです。
比較: 自分の方があの人より勝っている/あの人に比べて私はだめだ。
不満: なんで私ばかりこんな目に合うのが/なんで〇〇さんはいつも△△してくれないの。
不安: 一体どうなっちゃうんだろう、うまくいくのかなぁ
迷い: AかBかどっちにしたらいいんだろう、間違えて選びたくない。
まずは、小さなストレス、心の中の小さな「ひっかかり」に気づくこと
心の中の小さなひっかかりやストレスが、本当に小さいうちは、ほとんど気にならないかもしれません。
例えば、道路に枯葉が1枚落ちていても、目くじらを立てる人は少ないと思います。
でも、この小さなイライラざわざわに気がつかずに放置しておくと、ネガティブな感情がどんどん大きくなるのです。
これは枯葉に気がつかず放っておくとたくさん溜まって滑りやすくなったりするのと同じ感覚です。
反対に、この小さなイライラざわざわに気がつくと、どのように対応すれば建設的な方向にことが進むのか、自分で選べるようになります。
これは枯葉に気づいたら掃除をすることができる。毎日掃くのか、気になる時だけ掃くのか、完全にきれいにするのか、落ち葉の1~2枚は残しておくのか、そんなことも選べるようになります。
コツは、たまらないうちに対応すること

コツは、小さなストレス、小さなイライラざわざわが、たまらないうちに対応することです。
枯れ葉もあんまりたまると掃除が大変になりますからね。
毎朝、イライラざわざわが小さいうちに対応できると、とてもスッキリします。そして機嫌良く1日のスタートを切ることができるんです!
これが毎朝、私が呼吸のマインドフルネスをやったり、マインドフルなウォーキングをしたりする理由です。
この習慣が身に付いてから、1日の質が大きく変わりました。この習慣が積み重なったから毎日がとても楽になったのだと思います。
マインドフルネスは心の筋トレ

もう一ついいことがあります。それはマインドフルネスが心の筋トレになるということです。
どういうことかというと、毎朝、自分の心の中のイライラざわざわに気づき、それに建設的・意図的に対応することを繰り返していると、だんだんそのプロセスに慣れてくるんですね。
イライラざわざわに気づく→意図的に対応する、ということが早くできるようになるんです。
これは筋トレをすると腹筋が早くなるのと同じイメージです。
だからマインドフルネスは心の筋トレだと言われています。
これは単なるたとえではなく、実際に脳機能を調べても、マインドフルネスの実践を続けると、関係する脳神経が発達することがわかっています。
ストレス、つまり心の中にイライラざわざわがあること自体に、良い悪いはない
もう一つ、落ち葉のたとえで、気に入っていることがあります。
それは、ストレス、つまり心の中にイライラざわざわがあること自体に、良い悪いはないと言うことです。
例えて言うと、枯れ葉そのものに良い悪いがないのと同じです。秋になれば枯れ葉は落ちてくるものなのです。
同じように、生きていれば、ストレスは生まれ、イライラざわざわするものなのです。
大事なのはそのイライラざわざわに気づかないでいるのか、気づいて意図的に対応するのか、という点だけ、なのです。
マインドフルネスを実践している人に対するよくある誤解
マインドフルネスを実践している人はイライラざわざわしないんじゃないかという誤解があるようですが、そんなことはありません。
イライラざわざわするけれども、そこからすぐに「穏やかな状態」に戻ることができるというのがマインドフルネス実践者の特徴です。
まとめ
マインドフルネス(呼吸やウォーキングなど)実践すると自分の心の小さなイライラざわざわに気づくことができる。
気づくことができれば意図的に建設的な対応をすることができる。その結果、心が穏やかな状態に戻る
マインドフルネスは心の筋トレのようなもの。実践を重ねると心が「穏やかな状態」に戻るのが早くなる。その結果、気持ちが楽になる。
レレレのおじさんのモデルは、ブッダの弟子で「掃除」で悟りを開いた人であると言う説がある。
あなたもレレレのおじさんのようにご一緒に機嫌よくマインドフルネスをやってみませんか?
電子書籍「苦手なあの人との仕事が劇的に楽になる
『Google発』基本のマインドフルネスと5つの耐性アップ法」
毎日がんばっているあなたへ贈る
Googleが教えてくれた
誰にも振り回されずに
疲れない自分を作る方法
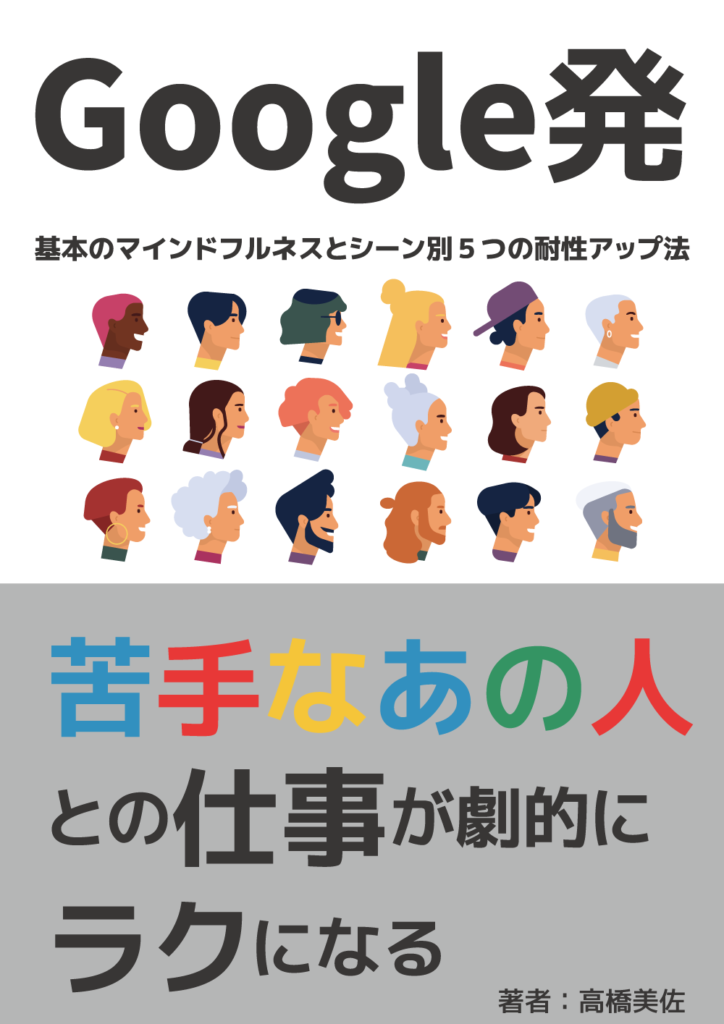
「苦手なあの人との仕事が劇的に楽になる
『Google発』基本のマインドフルネスと5つの耐性アップ法」
毎日がんばっているあなたへ贈る
Googleが教えてくれた
誰にも振り回されずに
疲れない自分を作る方法